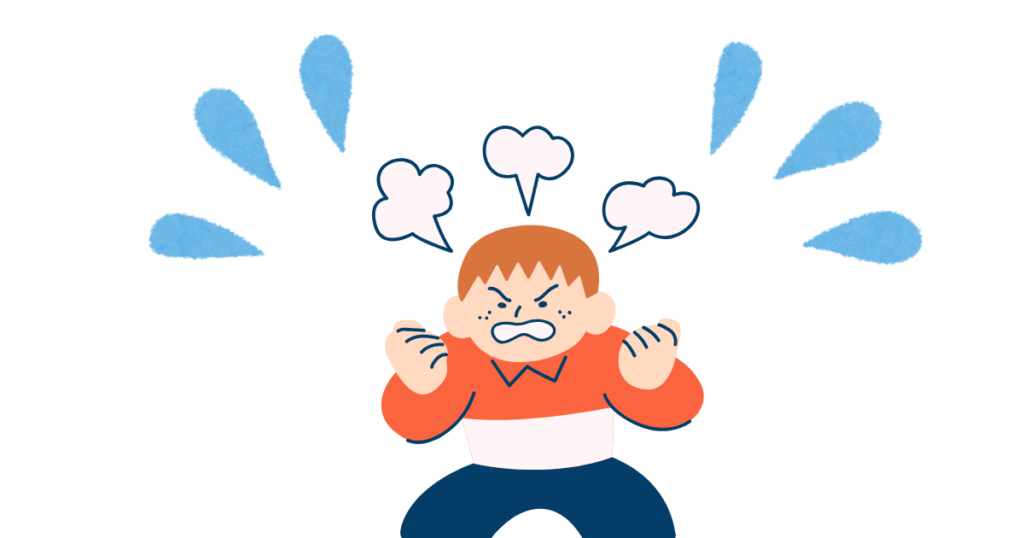
はじめに
突然泣き出す
大きな声で叫ぶ
ものを投げる
教室からの突然の飛び出し…
特別支援学校の現場では、
子どもがパニック状態になる場面に遭遇することが多々あります。
そんなとき
どんな声かけが必要か
どう対応すべきか
戸惑う先生も多いのではないでしょうか?
私自身、初めてパニックに遭遇した時は、
「怖い」
「どうしよう」
と、自分がパニックになりそうなぐらいの衝撃でした。
何もできず固まってしまった私…
先輩教員が支援しているのをただ見ているだけ…
そんな私の経験から、子どもたちのパニックに遭遇しても落ち着いて支援できるように
「パニック対応で大切にしている3つのこと」
を、ご紹介します。
パニック対応が大切なワケ
パニックは、子どもが「困らせようとして」起こしているのではありません。
多くの場合、
- 感覚刺激(音・光・におい)が強すぎた
- 予想外の展開に不安が高まった
- 気持ちを言葉にできず、感情があふれ出た
という外からは見えにくいSOSです。
そのため、対応を間違えてしまうと、
子どもはさらに混乱
子どもと大人の関係性も傷つく
可能性があります。
パニック時の関わりには、大人の感情ではなく理解と対応の視点が求められます。
寄り添う姿勢が支える安心感
私が以前、担任していたBくんのお話です。
予定変更が苦手で、自分の見通しと違い、思い通りにいかないと
机を蹴る
物を投げる
大声を出す
ことがありました。
ある日、給食のメニューが急に変更になってしましました。
Bくんは、配膳された給食を見て、
地団太を踏みながら
大きな声で泣き始め
その場に座り込んでしましました
初任の時であったら、私も固まっていたであろうこの場面。
しかし、理由がわかっていた私は
急がず、叱らず、ただ近くでこう伝えました。
「献立表と違うメニューでびっくりしたよね。
でも、大丈夫だよ。
一緒に給食見てみようか。」
Bくんを刺激しないよう、落ち着いた声量を心がけました。
10分後、少しずつ呼吸が落ち着いたタイミングで
「給食見てみる?」
と、声をかけると、おそるおそる給食をのぞき込むBくん。
おいしそうな匂いと、実物を見て安心できたのか、自分から席に戻り、食べ始めました。
子どもがパニックを起こすときは、心の中で混乱しているサイン
私たち教員は、子どもたちの心を理解して、「味方だよ」と伝えることで安心できる環境を
作っていくことが大切なのだと、改めて感じた出来事でした。
パニック時の対応で大切にしている3つのこと
「落ち着いてから関わる」姿勢を貫く
- パニック中は脳が戦う or 逃げるモードになっている
- 興奮しているときに、話しかけすぎたり、説得したりするのは逆効果
➔本人や他の子どもの安全確保を行い、落ち着くまでは刺激を減らす対応が基本です。
別室や、静かな場所に移動できるのであれば、環境を変えるのも良いですね。
「怒らず、動揺せず」が一番の安心材料
- 教員が怒鳴らない、不安げな顔を見せない
- 静かで穏やかなトーンを意識する
➔子どもは大人の雰囲気にとても敏感です。
教員の感情ではなく落ち着きで包む対応が信頼を生みます。
パニック後の回復時間を大切にする
- 自分から落ち着いて活動に向かえるよう「間」を入れる
- 「安心できる話題」「好きなもの」に触れる時間を作る
- 可能であれば、自分の行動を振り返る時間を作る
→ パニックはエネルギーの放出でもあるため、余白の時間でリセットできるよう支援します。
今日からできる小さな工夫
「完璧に対応しなきゃ」
「早く何とかしなきゃ」
と思えば思うほど、余計に焦ってしまうもの。
でも!
小さな工夫や準備で、落ち着いた対応をすることができます。
今日からできる対応
- 「刺激が少ない落ち着きスペース」を1か所用意しておく
- 「パニックの前兆」を記録して担任間、学年間で共有する
- 「気持ちカード」や「今の気分カード」を準備しておく
こんな声かけ例もおすすめ
- 「大丈夫、ここにいるよ」
- 「落ち着いたら話そうね」
- 「どうしても嫌だったらいいよ、あとで先生と考えよう」
➔今すぐ答えを出さなくていいという余白が、子どもに安心をもたらします。
おわりに
パニックは、「わがまま」でも「甘え」でもありません。
その子の精一杯のサインです。
教員として私たちがすぐにできることは、
・自分が落ち着く
・怒らない
・焦らない
そして、「大丈夫だよ」と安心を届ける関わり方です。
私たちが落ち着いて、どっしり構えていることが、子どもたちの安心につながります。
子どもたちの心に寄り添って、安心感を与える支援をしましょう🌟
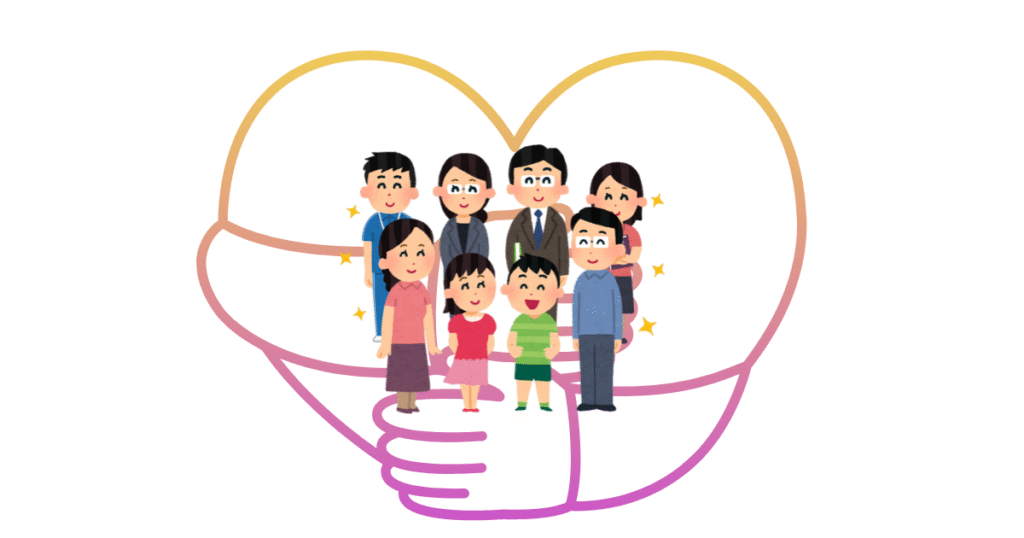
今後も、特別支援学校の授業づくり・支援の工夫について発信していきます。
質問や感想など、コメント大歓迎です♬
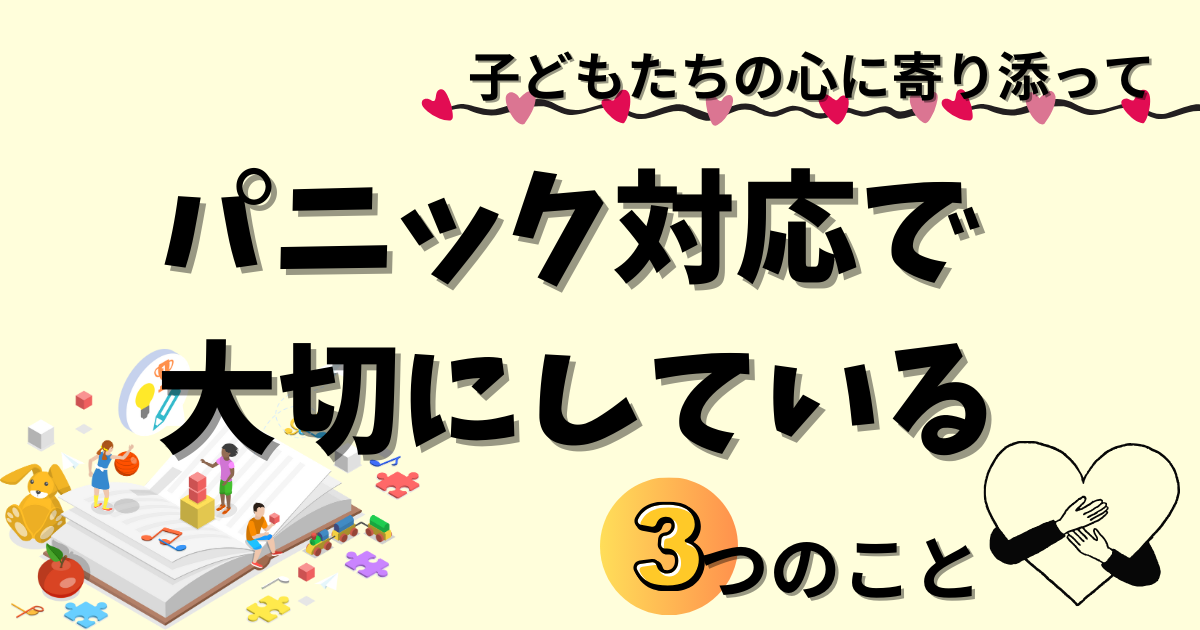
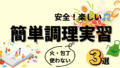
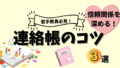
コメント