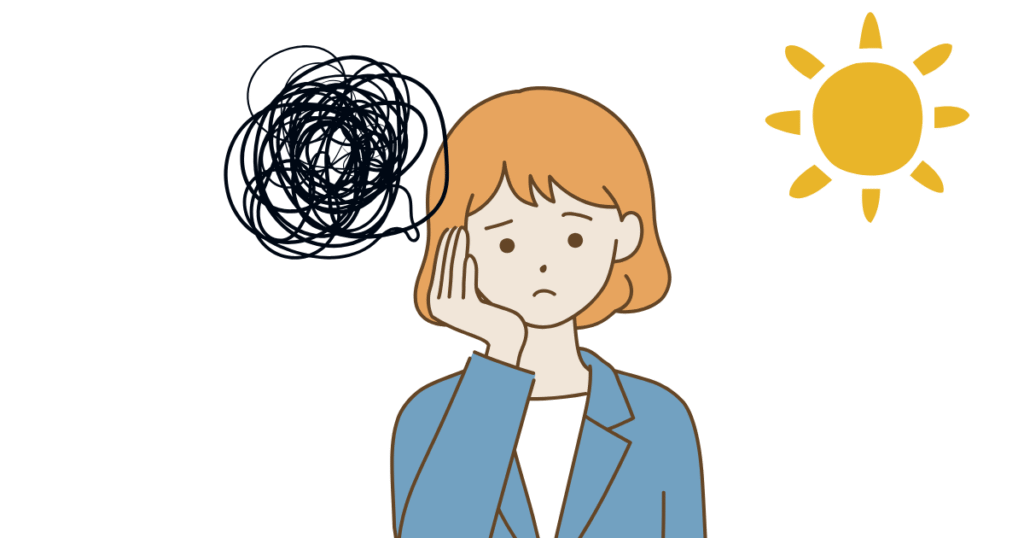
はじめに
「朝の会がざわざわして進まない…」
「子どもたちの集中力がもたない」
「日によって反応がバラバラで、うまくいかない…」
など、そんな悩みを抱えていませんか?
朝の会は、
1日のスタートを整える大切な時間 です。
でも、特別支援学校では
「集中できない」
「気持ちが切り替わらない」
「自己刺激に没頭してしまう」
などといった理由で、思うように進まないことも少なくないのでは?
朝の会をスムーズに、安心できる時間にするための工夫を、ご紹介します!
なんで朝の会がうまくいかないの?
「ちゃんとやっているはずなのに、どうしてうまくいかないの?」
と、自信を無くしていませんか?
まずは、うまくいかない原因を考えてみましょう。
特別支援学校の子どもたちは、
- 毎朝の体調や気分の差が大きい
- 活動の見通しが持てずに不安になる
- 活動と活動の切り替えが苦手
などの特性を持っていることが多くあります。
個々によって特性は様々ですよね。
つまり、
「やり方が悪い」のではなく、活動の仕組みがその子に合っていないだけなんです。
朝の会ってどんな活動があるの?
学校や学部、学級によって違いはありますが、主な活動は次の通りです。
- あいさつ(おはようございます)
- 出席確認(呼名、返事)
- 日付・天気の確認(〇月〇日〇曜日、天気は〇〇)
- 今日の予定の確認(1、朝の会 2、朝の運動 3、生活単元 …)
- 今日の給食(今日の給食は、カレーライスとサラダとプリンです…など)
- 連絡事項(雨なので、教室で遊びましょう…など)
このような活動の中で、
「ざわつきやすい」
「集中しづらい」
といった課題がある場面は、どの部分なのかを抽出します。
課題となる場面に、見通しや安心感を与える工夫は何かを考えていきましょう。
スムーズに進めるコツ5選!
ここからは、現場で実際に役立つ朝の会がラクになる工夫を5つご紹介します!
「視覚スケジュール」で見通しをもつ
▶ホワイトボードやカードで、朝の会の流れを見える化します。
イラストだけ、文字とイラスト、文字のみなど、実態に応じて提示するとGOOD!
「次はなに?」「いつ終わるの?」がわかるだけで、安心感が上がります♪
「自分の番が来る」がわかる工夫
▶出席確認などは、子どもの写真カードを使って順番を可視化します。
「待つのが苦手」な子でも、自分の番はどこか見通しを持つことで、落ち着きやすくなります。
1人1役で関わる場面をつくる
▶日替わり日直や、日付を読む人、給食発表をする人など役割を設定します。
自分の役割を楽しみにしたり、参加している感覚があったりすると、自然と集中力もアップ!
身体を使う活動を取り入れる
▶始まりの合図に「手遊び」「朝の会の歌」などを取り入れると、切り替えがスムーズになります。
身体を動かすことで、気持ちも切り替わり、みんなで動くことで一体感も生まれます。
「楽しい!やってみたい!」活動を1つ入れる
▶絵カードで今日はどんな気分かを選んだり、楽しみな活動や、頑張り宣言などを取り入れたりするのもいいですね。
自分の気持ちを表出することで、コミュニケーションの力もつきます。
今日から使えるおすすめ活動
すぐに実践できる、簡単・効果的な朝の会ネタを5つ紹介します!
朝の手遊び
▶「グーチョキパーでなにつくろう」など、知っている曲や手指を動かすことで集中を促す
子どもたちにどんな曲をやりたいかを聞くのもいいですね😊
天気カードで窓から空を見てみよう!
▶実際に外を見て選ぶことで、マッチング力や思考力、自発性がUP!
今日の気分を選ぶボード
▶表情イラストから今の気持ちを選んで発表
予定カードを順番に貼っていく
▶活動ごとにカードを1枚ずつ貼り、みんなで「1日をつくる」感覚に!
「今日の一言決意発表」くじびき
▶簡単な言葉(例:がんばるぞ!)などを引いて、みんなで宣言することで朝の雰囲気が明るくなり、一体感も見られます。
おわりに
朝の会は、ただの朝の儀式ではありません。
子どもにとって
「今日も学校に来てよかった」
と思える大事な時間となります。
そのスタートがうまくいくと、教員も子どもも1日の気持ちがぐっと軽くなります。
大切なのは、
「その子に合った形で安心できる時間をつくること」
です。完璧じゃなくていいのです。
ちょっとした工夫の積み重ねで、朝の会はどんどん良くなっていきますよ!
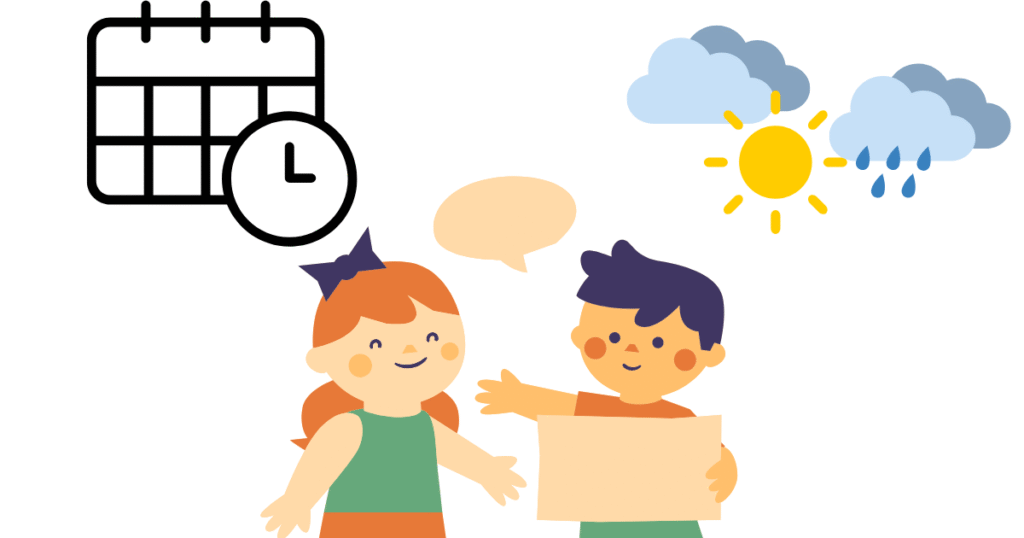
今後も、特別支援学校の授業づくり・支援の工夫について発信していきます。
質問や感想など、コメント大歓迎です♬
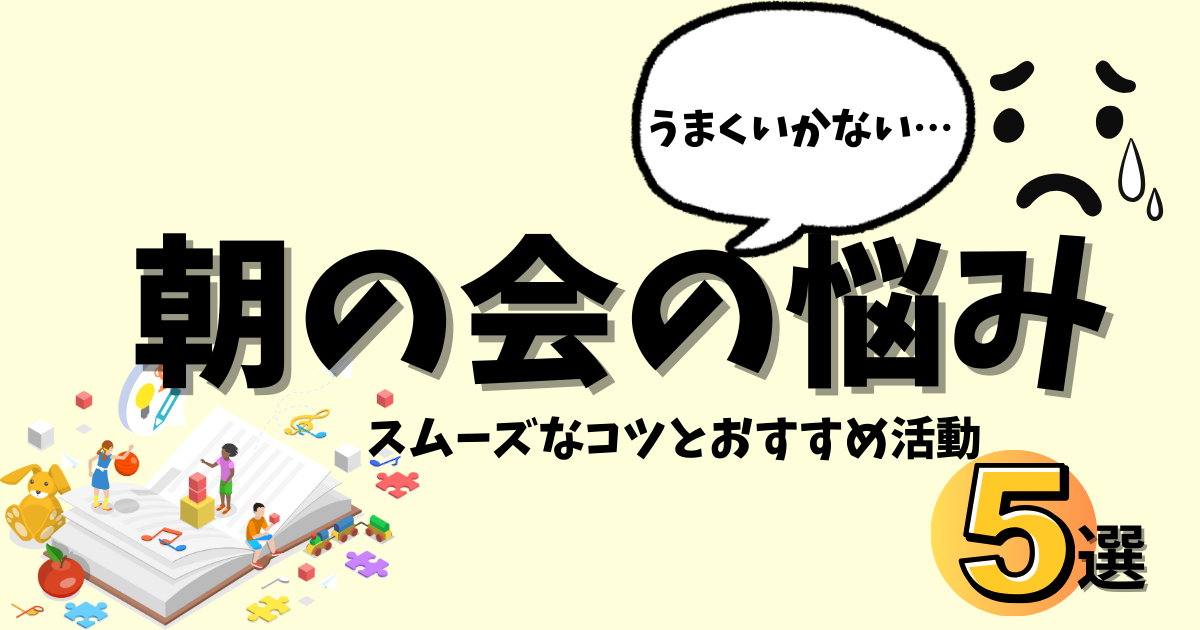
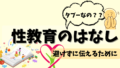
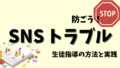
コメント