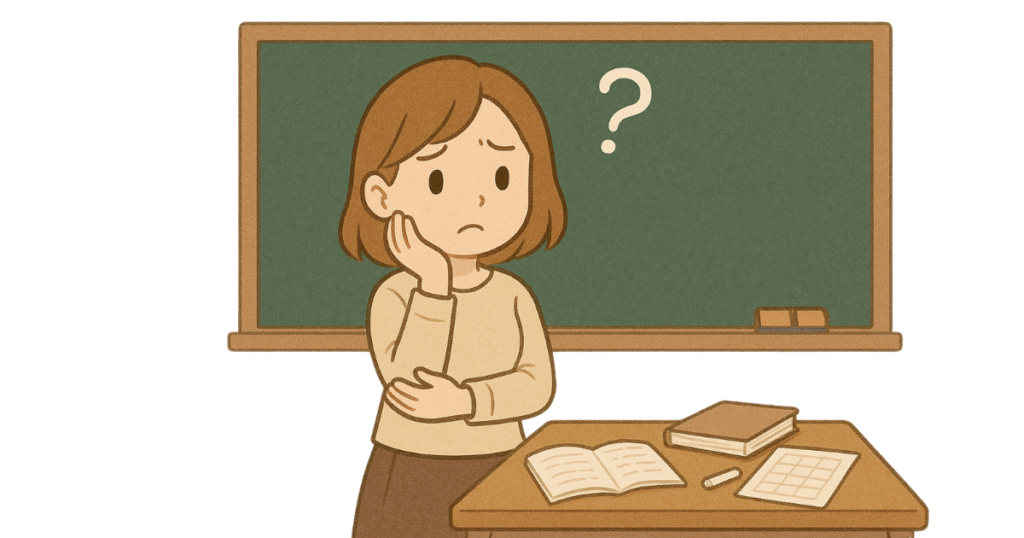
はじめに
「来週の授業、何しよう…」
「教材が毎回ワンパターンになる」
「国語に生活単元、自立活動…複数の授業を作らなきゃ」
特別支援学校の現場で、教員がぶつかりやすい壁のひとつが
授業や教材のネタ切れ
教科書のない現場なので、教員それぞれの知識・技能が問われます。
事務仕事や会議に追われて、じっくり考える時間がないのも悩みの一つですね。
でも実は!
少し視点を変えるだけで、
身の回りのものや行事を教材に活かすヒントはたくさんあるんです!
教材づくりが大変なのはなぜ?
特別支援教育の教材づくりが難しい理由は、大きく3つあります。
●子どもによって理解の仕方や興味が大きく違う
●教員のスキルに左右される
●自作教材に時間がかかるのに、反応が薄いとモチベーションが下がる
この「労力と成果のズレ」が、
モチベーションの低下や
ネタ切れ感
につながりやすいのです。
でも大丈夫です!
教材は「特別なもの」じゃなくていい。
「子どもが反応する」
「できた」「わかった」が見える
「教員もラク」
がそろえば、それは立派ないい教材です!
ネタ切れしない教材ってどんなもの?
ネタに困らない教材には、ある共通点があります。
- 日常にあるものを使っている(紙コップ、洗濯ばさみ、100均グッズなど)
- 活動の型がシンプル(貼る・並べる・ひも通し・マッチング など)
- 季節や行事とつながっている(クリスマス、七夕、誕生日など)
これは、難しく考えすぎず、使いやすい素材と型を持っておくことが、
ネタ切れしない授業への近道となります。
授業づくりがラクになるアイディア
教科・領域ごとに使える授業例をご紹介します。
【国語・生活単元】絵カードクイズ
▶例:「〇〇はどこにある?」「〇〇ってどんな道具?」「〇〇といえば?」
写真やイラストを見せて、選択肢から選ぶだけでも、楽しい授業になります!
【図工・生活単元】ちぎり絵アート
▶例:「季節の制作(花火・お月見・ハロウィンなど)」
自由度が高く、発達段階に合わせて調整しやすい万能ネタです。
図工で作ったものを、生活単元で活用…など、授業コラボをいいですね🌟
【算数・行事事前】「おかいものごっこ」
▶例:お金のマッチング/お金を払うごっこ遊び
100円ショップのアイテムや手作りお金カードで、体験的な学習ができます。
【SST・行事・特別活動・学級活動】あいさつビンゴ
▶例:あいさつの種類(ありがとう、ごめんなさい、こんにちは)をビンゴ形式で取り組む
ゲーム性があることで、楽しみながら人との関わりを学べます。
【音楽・特別活動・学級活動】音当てクイズ
▶例:鈴・太鼓・カスタネットの音を聴いて当てる
音楽が苦手な子でも「聴いて・答える」なら取り組みやすいです。
今日から使えるネタ5選
忙しい先生向けに、準備がラク・すぐできる 活動アイデアを5つご紹介です!
紙コップ積みあげゲーム(数量・手指の活動)
▶紙コップ10個だけでOK!
「同じ色を重ねる」「高く積む」などルールを工夫すれば、何回でも楽しめる定番教材。
季節のぬりえ+アレンジ(図工・行事)
▶市販や無料のぬりえに「自分の顔を貼る」「シールで飾る」など一工夫でオリジナルに。
カラーひも通し(手指の活動・図工)
▶100均のビーズとカラーモールだけで、見た目もかわいい教材に!そのまま作品にもなります。
ねらいに応じて、数を数える、順番を守るなども組み込めます。
スケジュールカードで今日の流れを確認(自立活動・生活単元・日常生活)
▶朝の会や活動の合間に、「今は何の時間?」をカードで提示。
見通しが持てることで安心につながります。
イラストしりとり(国語・自立活動)
▶絵カードやホワイトボードを使って、友達や教員と絵しりとりを楽しもう。
難易度調整もしやすく、他者との言葉のやりとりにも広がります。
おわりに
「いい教材をつくらなきゃ」と力が入るほど、授業づくりは苦しくなります。
しかし!
- 身近なものに目を向ける
- 活動の型をストックしておく
- 楽しい!できた!と感じた瞬間を大事にする
この3つを意識するだけで、日々の教材づくりがぐっとラクになるはずです。
完璧じゃなくていいんです🌟
「今日も1つ、楽しい授業ができたな🎵」
そう思える授業が積み重なることで、教員も子どもも成長していくのです。

特別支援学校の授業づくりに役立つ情報を、今後も発信していきます!
コメントや感想も大歓迎です♪
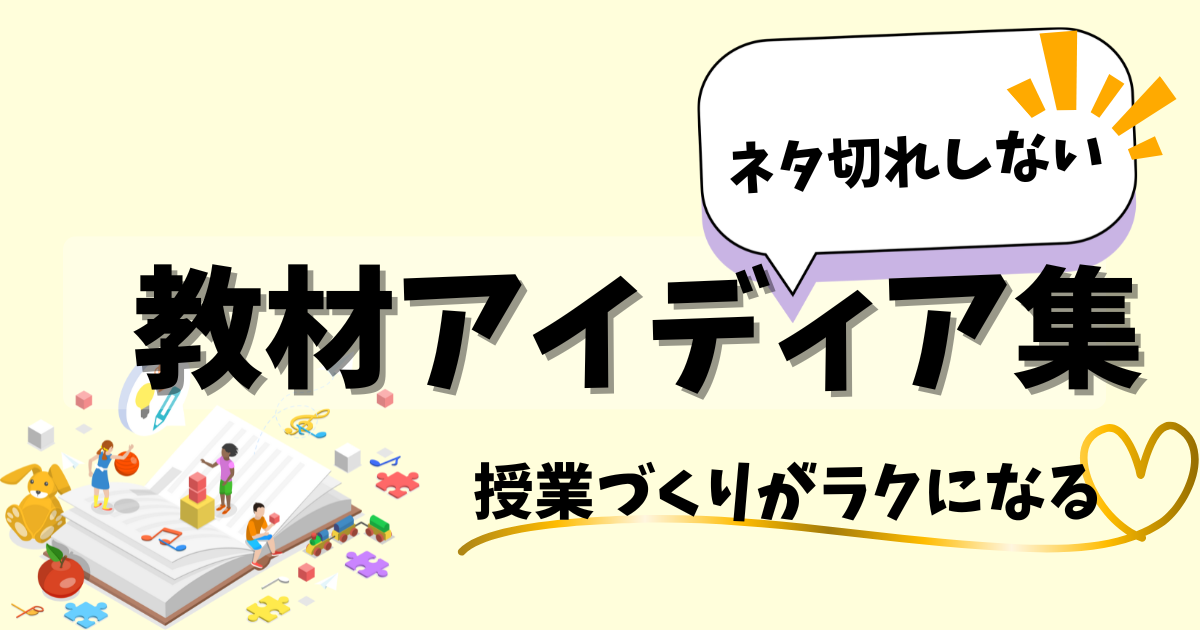
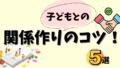
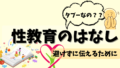
コメント