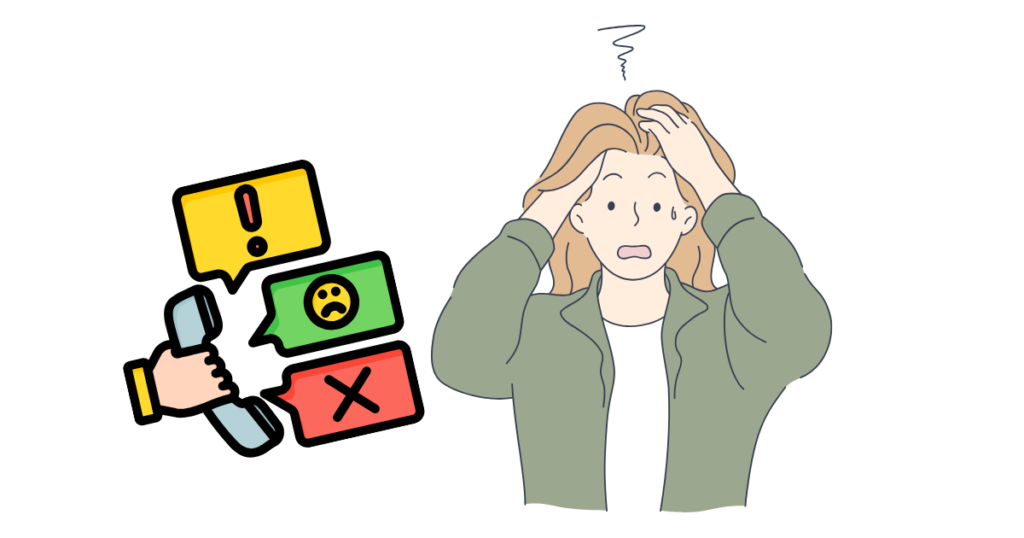
特別支援学校で働きはじめたばかりの若手教員にとって、
子どもとの関わり以上に緊張するのが「保護者対応」ですよね。
「どんな風に話せばいいの?」
「クレームになったらどうしよう…」
そんな不安を感じている先生は多いのではないでしょうか。
今回は、若手教員がよく直面する
保護者対応の壁と、
保護者と安心して関われるようになるヒントを、お伝えします。
保護者対応は難しい??
若手教員が保護者対応に戸惑う理由は、大きく3つあります。
- 教員としての自信がまだ育っていない
- 自分よりも年上の保護者が多く「相手は人生の先輩」という気後れ
- 子育ての経験がないと、子どもに関することで‶何が正解”がわからない会話が多い
つまり、
自分の中に「正しく伝えられるか不安」という気持ちがあるほど、
緊張してしまうのです。
実は、保護者も同じように不安を抱えています。
例えば…
「学校でうまくやれているかな?」
「うちの子、大丈夫かな?」
「先生に迷惑かけてないかな」
そんな気持ちに寄り添うことが、対応の第一歩です。
よくある 「ぶつかりがちなポイント」3つ
ここでは、実際に現場でよくある‶ぶつかりポイント”を紹介します。
連絡帳や電話での「言葉選び」
「気になる行動があった」
「ケンカをした」など、ネガティブで伝えにくい内容のとき、表現に迷ってしまう人は多いはずです。
伝えないといけない内容だけど、自分が責められるのでは?と、
悪い方向に考えてしまいますよね。
事例:AくんとBくんがおもちゃを巡り、お互い掴み合うケンカが起きた。
今回ケガはなかったが、今後も同じことが起きるかもしれないので、
お互いの家に電話で連絡をすることにした。
↓↓↓電話対応例↓↓↓
「AくんとBくんが同じおもちゃで遊びたいと順番を巡って、ケンカになってしましました。
今回ケガはありませんでしたが、大きなケンカだったのでご連絡しました。
お互い、落ち着ける場所で教員とやりとりをすると、順番に遊べばよかったと、自分の
行動を振り返ることができ、最後は『ごめんね』と、仲直りすることができました。
今後も同じような場面が想定されますが、安全面を確保しながら様子を見て
適切な支援指導を行っていきます。」
このように
‶事実ベース+子どもへの対応+見通し”をセットにして伝えると、保護者も安心します。
保護者とのでの温度差
「うちの子は家ではできるんですけど…」
という言葉に焦ってしまったことはありませんか?
どの子でも 学校の自分 と 家での自分 が違うことがあります。
これは、私たちも同じではないでしょうか?
場面や環境の差によって、子どもたちが出す力も変わってくるのです。
逆に 学校だとできていることが、家ではできていない なんてこともあります。
これはよくあることですので、特別なことではありません。
しかし、保護者にとってみれば
「なぜ??」
「学校の指導が悪いのでは?」
と、思ってしまいがちです。
そこで、
「学校と家庭の視点の違い」を共有するのがカギ です。
「家では本当にできているんですか?」
など、真っ向から否定せず、
「ご家庭でできている様子をぜひ知りたいです」
「学校でも安心して力が出せるように支援を工夫していきます」
「教えてくれて助かりました」
と一緒に探るスタンスでお話ししましょう。
保護者の不満・不安との向き合い方
「学校がもっとこうしてくれたら…」
と言われ、つい落ち込んでしまうことも。
自分では一所懸命やっているのに、認めてもらえないと悲しいですよね。
「自分はちゃんと子どものことを考えているのに…」
「なんでわかってくれないんだ」
「自分は教員に向いていないのではないか」
どうしてもネガティブに考えてしまします。
そんな時は、発想を変えてみましょう。
「責められている」ではなく「頼られている」と捉えてみましょう。
「ご意見ありがとうございます。」
「担任間や学年でも共有させていただきます。」
など、一言添えるだけで、
「今後のことも考えてくれているんだ」と、印象も大きく変わります。
保護者への対応力を上げる3つの実践スキル
「聴く力」を意識する
- 相手の話を最後までさえぎらずに聴く
- うなずきや相づちを忘れずに
- 話の意図をくみ取って、返す言葉を選ぶ
教員がずっと話すのではなく、保護者と教員は7:3ぐらいの割合で
保護者が話す時間を設けましょう。
これだけで、相手の印象はぐっと良くなります。
明るい話題は、笑顔で聴く、ネガティブな話題は真剣な表情で…
といったように、聴く表情も意識するとなお良いです。
伝え方のテンプレートを持っておく
例えば
【よかったこと→気になったこと→今後の支援】
または
【気になったこと→改善できたこと(よかったこと)→今後の支援】
などの順で伝えることで、話の流れがスムーズになります。
「今日は〇〇がよくできました。ただ、××の場面で△△が見られました。
今後は、□□の支援を行っていきます。」
自分なりのテンプレートがあると、焦らずに済みます。
1人で抱え込まない
「この言い方でいいかな?」
「これは伝えてもいいのかな?」
と悩んだときは、先輩や管理職に相談するのが鉄則!
経験のある人からのアドバイスで、気持ちがぐっとラクになります。
自分の味方がいることで安心しますよね♪
その時のためにも、同僚の先生方とコミュニケーションをとっておきましょう。
今日からできる小さな工夫3つ
●連絡帳には必ず「ポジティブな一文」を添える
➡子どもの良い面を伝える習慣が信頼につながります。
●面談前に「伝えたいことメモ」を作っておく
➡伝えたいことを整理することで、焦らず話せます。
●「保護者もチームの一員」という意識をもつ
➡学校・家庭・子どもが一体となる関係づくりが、子どもにとっても安心のベースです。
完璧じゃなくていい。「伝えようとする姿勢」が伝わる
保護者対応に正解はありません。
でも、‶伝えよう・寄り添おう”という気持ちは、必ず相手に届きます。
困ったときは、ひとりで抱え込まず、同僚や管理職に相談しながら一歩ずつ進んでいきましょう。
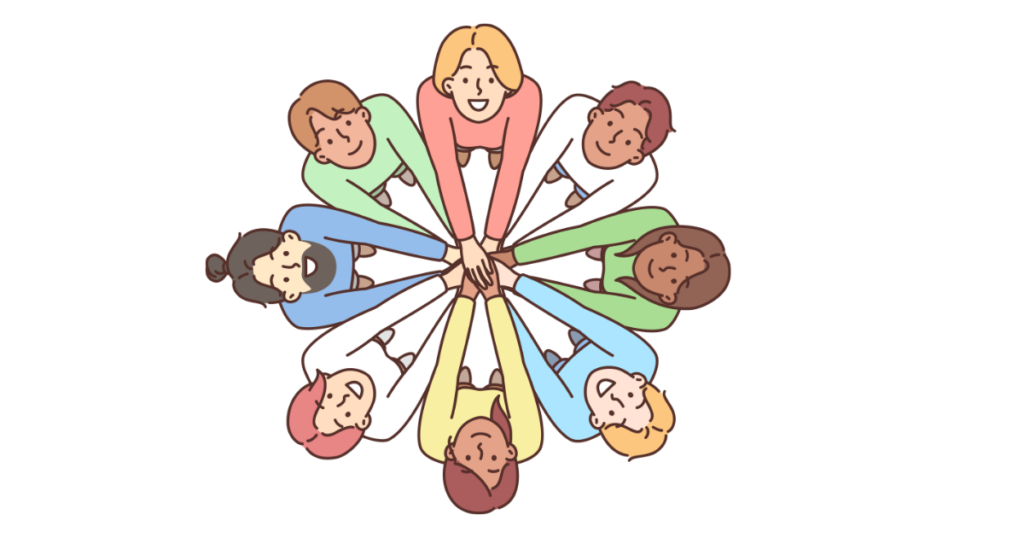
この記事を最後まで読んでいただきありがとうございました。
ご質問等はコメント欄やお問い合わせ欄からどうぞ!
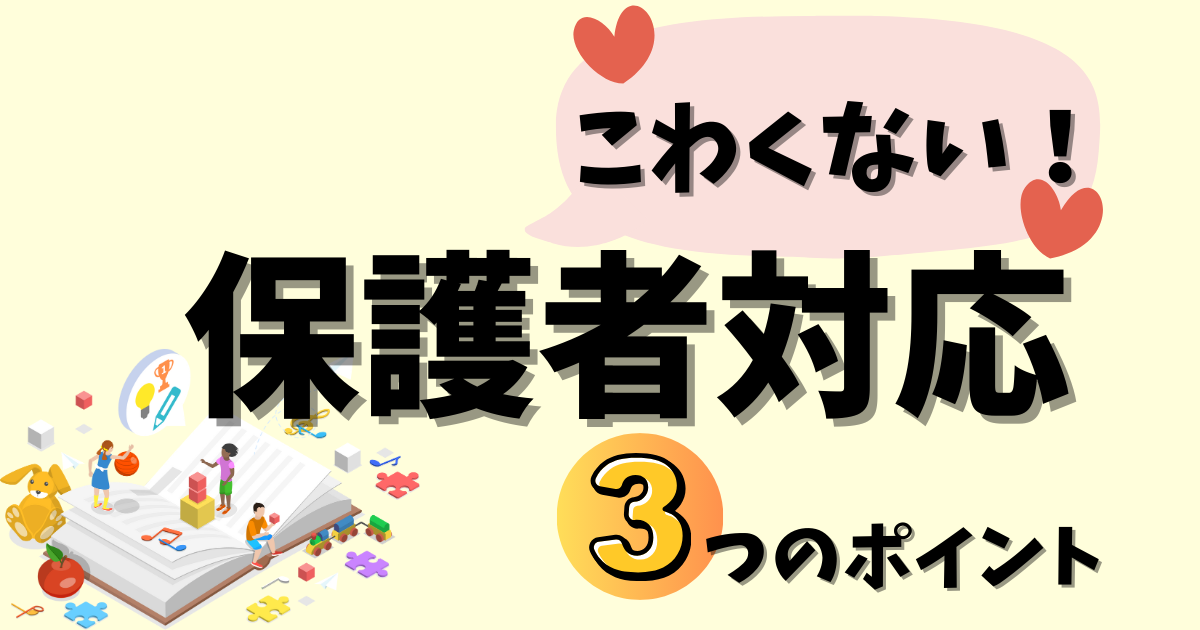

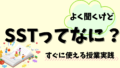
コメント