
「保護者とのやりとり、難しい…」
「ちゃんと信頼してもらえてるかな…」
「クレームがきたらどうしよう…」
特別支援教育の現場では、(どの学校現場でも同じですが)
子どもだけでなく保護者との関係づくりもとても大切です。
でも!その関係づくりをどう作ったらいいか…と
悩んでいる先生も少なくないはずです。
これを読んで、「あ、私もできるかも」と思ってもらえたらうれしいです!
保護者との関係が特別支援教育の土台になるワケ
教員と保護者は‶支援のチーム”
保護者は、子どもにとって最も信頼できる存在です。
そんな大人と教員がパートナーとして協力できる関係を築くことで、
支援はより確実なものになります。
関係づくりは、次のような価値を生みます。
- 教員と保護者が「同じ方向」で子どもを見られる
- 子どもが学校でも家庭でも安心できる
- 支援方針のすり合わせがスムーズになる
- 保護者自身の自己肯定感が高まる(=子育てへの自信)
つまり、
保護者との関係は「子どもの支援の質」を左右する大事な土台なのです。
嬉しい!関係が深まった瞬間
「先生に聞いてもらえて安心しました」の一言✨
学校では、癇癪も少なく「いい子」タイプのAくん。
しかし、家では…
●思い通りにならないと暴れる
●すぐにイライラする
●兄弟が怒られていると泣く
などの困り感がありました。
困り感がどの程度なのか、どう対処しているのか気になり、
連絡帳にて
「ご家庭での様子を時系列で詳しく教えていただけますか?」
「可能ならば、面談しませんか?」
と伝えました。
返信は…
「ぜひ、お願いします」
とのことだったので、すぐに日程調整し、面談を実施しました。
その場で、Aくんの家庭での様子が詳しく聞け、
〇困り感が起きるタイミング
〇家ではどんな言葉かけ等を行っているか
〇学校ではどのように気持ちを切り替えているか
などをじっくり話しました。
次の日、保護者の方から
「先生に聞いてもらえるだけで心が楽になりました」
「子どものことが さらにわかりました」
との言葉が✨
学校と家庭で、子どもへの対応が共有されたおかげで、
子どもの様子も少しずつ落ち着いていきました。
‶困っているのは、どちらか一方じゃない”
そう思える関係が、保護者との信頼につながっていくのだと実感した瞬間でした。
私が大切にしている関係づくりの3つの工夫
①「否定しない」スタンスを持つ
保護者の話を聞くときは、まず「そうだったんですね」と受け止めること。
つい意見したくなる場面でも、「まず聞く」が信頼の第一歩です。
成長だけでなく「その子らしさ」を伝える
「できるようになったこと」を伝えることは大前提!
その他にも
「今日こんなことがありました!」
という日常の中の素敵な瞬間を伝えるようにしています。
保護者は学びより‶その子らしさ”に喜びを感じることも多いです。
連絡帳や面談で‶ひとことの共感”を添える
例えば
- 「○○くんらしいなと思いました」
- 「昨日のお話、とても共感しました」
- 「○○さんの対応、とても素敵でした」
小さな言葉でも、気持ちをぐっと近づけることが信頼感を上げるできます。
今日からできる‶関係づくりのヒント”
保護者の努力を前向きに認め、称賛する
➡結果だけでなく、過程を見てもらえることで、保護者は安心します。
連絡帳の最後に前向きな「ひとこと」を添える
➡短くてもOK!心のこもった一文が信頼を生みます。
保護者の話を‶最後まで聞く”ことを意識する
➡解決策よりも「共感」が欲しいときもある。
じっくり耳を傾けることが、何よりの支援になります。

保護者との関係は、とても繊細でなものです。
「うまくいかないな」
「距離がつかめないな」
そんなときこそ、自分のスタンスを振り返るチャンス。
‶信頼される姿勢”を持つことが、きっと子どもの支援につながっていきます。
あなたのそのひとことが、保護者の心を軽くするかもしれません。
この記事を最後まで読んでいただきありがとうございました。
ご質問等はコメント欄やお問い合わせ欄からどうぞ!
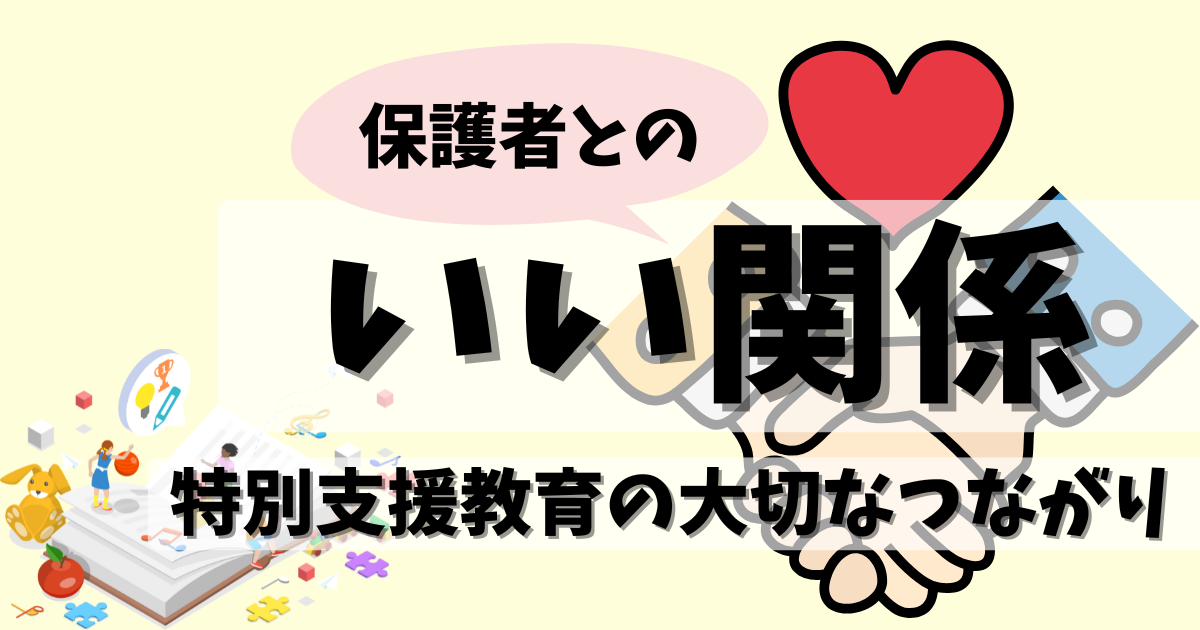
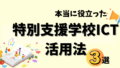

コメント