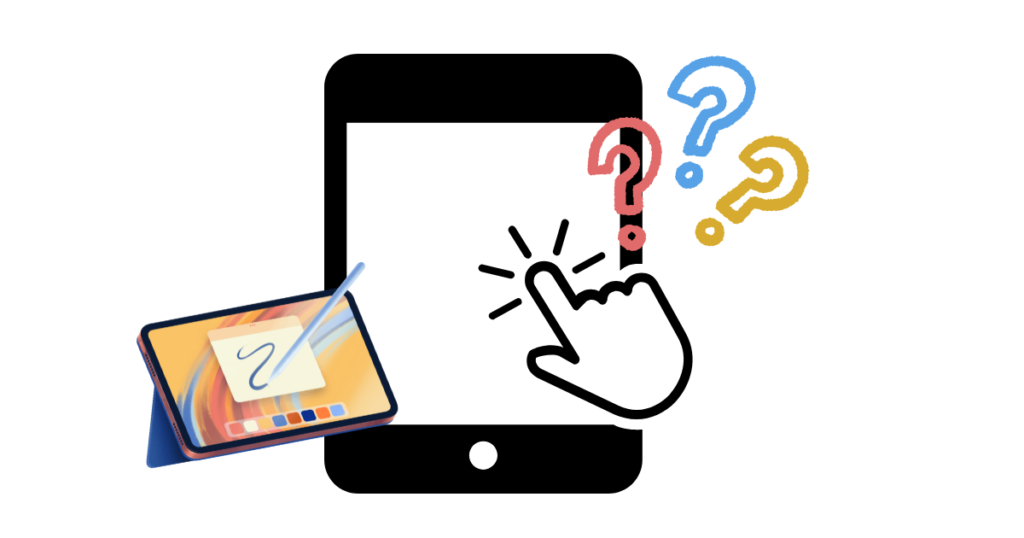
「ICT教育を!って言われているけど、何のこと?」
「ICTって便利そうだけど、実際みんなどう使ってるの?」
「特別支援の現場で意味あるのかな?」
そう思ったことがある先生いませんか?
実は…私自身も、ICTという言葉がでてきた当初は、
「私が担任している子どもたちに合うのかな?」
「知識もスキルもないのにできるの?」
と疑問を感じていました。
でも今では、
子どもの‶できた!”を引き出す大切なツールのひとつになっています。
特別支援教育にICTが有効なワケ
🌟「個別支援の最適化」と「安心感」を支えるツール
ICT(タブレットやアプリなど)は、特別支援教育において
個別支援のための多様なアプローチを補う大きな武器になります。
例えば
- 書字や発語が苦手な子の「代替手段」になる
- ひとりひとりの実態、理解度に応じた「個別支援の最適化」がしやすい
- 注意が散りやすい子も、視覚的、聴覚的アプローチで「集中しやすくなる」
など、支援の幅が広がり、より「個」に応じたアプローチが可能となります。
支援を受け、子どもたちの「できた」が高まることで安心感にも繋がり、
良い循環が広がっていくのです。
ICTの導入は、「できない」「わからない」という子どもたちの不安から
「やってみたい」
「できた」への
橋渡しになります。
ICTで!子どもたちの「変化」が教えてくれたこと
🌟子どもたちの反応がガラッと変わった!
●書字が苦手で、プリントだと書くことに抵抗感があったのあった子
➡タブレットには、笑顔でタッチ!自分の指を使って運筆に取り組むようになった♪
●アプリのアイコンによる意思表示で、安心感や参加意欲を引き出す
➡うまく話せなくても、コミュニケーションアプリのアイコンを押すと、安心して意思がだせる
●アプリのカレンダー機能を使えば、日課の確認がすぐにできる
➡見通しが持てるようになることで、活動にスムーズに取り組めるようになった!
ICTは「できないことを補う」だけでなく、
「安心できる環境を提供」
「得意を伸ばす」
ことにもつながっているのです。
現場で使った!ICT活用法3選
写真アプリやプレゼンテーションアプリでスモールステップを見える化
【活用例】
活動手順やルールを写真や文字で「やること」をリスト化
🌟効果 視覚で流れがわかり、子ども自身で確認できるようになる
DropTalkアプリでコミュニケーション支援
【活用例】
言葉の表出が苦手な子がアイコンをタッチすることで「トイレに行きたい」など意思表示
🌟効果 伝わらないことによる不安やパニックが減り、安心して活動できるようになる
Kahoot! やPowerPointのクイズで楽しく授業参加
【活用例】
選択肢式のクイズやゲーム形式の授業復習タイム
🌟効果 タッチ操作で正解を選ぶことで体験的に「できた!」の積み重ねができる
明日から試せるICT活用ミニアイデア
写真+音声で「視覚支援カード」を作ってみる
タブレットで撮影+録音するだけで、自分専用カード完成!
動画で「活動の見通し」を伝える
教員が実演した動画を見せると、絵カードより理解しやすいこともある!
制作活動や調理などで大活躍✨
2択表示だけでも‶選ぶ力”が育つ
自己決定の経験を積む機会にもなり、成功体験を増やせる
特別支援教育におけるICT活用は、
効率化ではなく、「その子に合った学び方を広げること」が目的です。
- 見える化で安心
- 表現の手段を増やす
- 楽しさで興味関心を引き込む
など、ほんの小さな活用でも、子どもたちの「できた!」につながります。
まずは一つでも、試してみてください🎵

この記事を最後まで読んでいただきありがとうございました。
ご質問等はコメント欄やお問い合わせ欄からどうぞ!
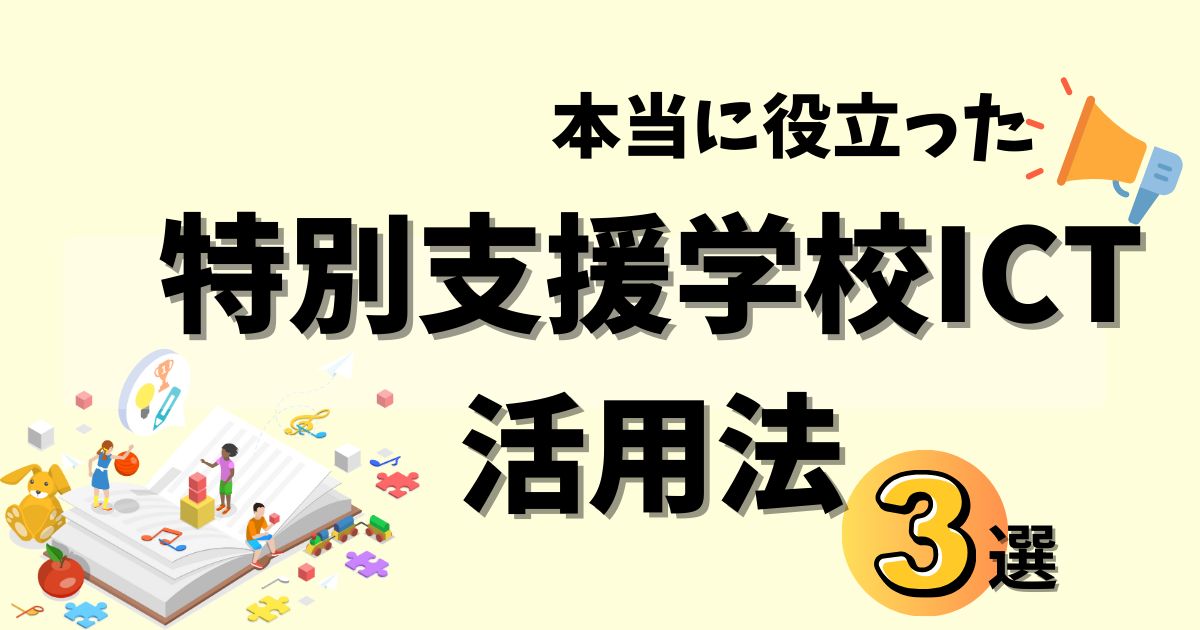
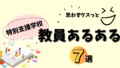
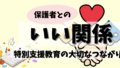
コメント