
「明日の授業の準備が終わらない…」
「教材づくりは土日にやるしかない」
「子どもたちの反応がイマイチ」
特別支援の現場で、こんなこと思っている先生はいませんか?
何を隠そう…私は思っていた一人です!
もともと特別支援のことを全く知らずに配属された私。
中学校の家庭科教諭の予定で実習を行ってきたので、
始めはカルチャーショックが大きく、教科書がない授業づくりに戸惑う毎日でした。
とにかく特別支援教育を学ぶところから始め、先輩教員のマネをしながら授業づくりをスタート。
放課後の会議や研修が終わったあとから、ひたすら授業作りの作業。
土日祝日など休日もひたすら作業…
しかし、これだけ時間をかけているのに
生徒たちの反応はというと
「…………???」
ひどい時は、見通しが持てずパニックになってしまう生徒まで…
私の自己肯定感は下がり続け、「辞めたい」と本気で思うようになりました。
でも!何か1回でも子どもたちの「できた」が見たいと考え、再び試行錯誤の日々を開始…
子どもたちの反応や、先輩たちが行っている授業を観察しなおすと、ちょっとした3つの工夫で
●授業準備が楽に!
●授業をするのが楽しくなる!
●子どもたちの「できた」の反応が見える
という実感がもてました🎵
今回は、私が授業づくりの負のループから抜け出した3つの工夫を教えます!!!
100円ショップで!低コストで幅広く使える教材づくり
知的の特別支援学校では、教科書を開いて、板書して…という授業スタイルではありません。
子どもたちは5感をたくさん使って、体験的に学ぶことがとても大切です。
それなら特別な教材を使った方がいいんじゃないの?
と、思うかもしれません。もちろん市販で売っている教材を使うのも悪くないです。
しかし、市販で売っているものは、
そう!
「高い!!」
勤務校にあればいいですが、個人で準備するにはコストがかかりすぎます。
そこで使えるのが
100円ショップ!!!
今の100円ショップは品数も、クオリティも高く宝石箱だと私は思っています(笑)
私がよく活用しているものは
●ホワイトボード
●洗濯ばさみ
●カラーポンポン
●プラスチック容器
●プールスティック
●シール
●マジックテープ
などなど
活用例としては
手指の巧緻性課題➡マジックテープ、洗濯ばさみ
色や形のマッチング➡カラーポンポン、シール
100円ショップのアイテムで十分使えました。
子どもたちも視覚的にも感覚的にも、「できた」を感じやすく、
なくしたり、壊れても、すぐに再提供できる手軽さも魅力です。
ちょっとした「ゲーム化」で子どもたちのやる気が倍増!
特別支援学校の授業では、「繰り返し」学習で知識や技能の定着を図ります。
何度も何度も「できた」を繰り返し、スモールステップで取り組みます。
しかし、何度も繰り返すということは
「飽きる」
ことにも繋がるのです。
特に単純作業な学習ではすぐに飽きて、学習への意欲も低下してしまいます。。
そこで!
私が取り入れたのは
ちょっとした「ゲーム化」
実践例だと
●ひらがなビンゴ
●コミュニケーションすごろく
●タイマーを使った物の弁別活動
です
これらを取り入れることで、
子どもたちが目を輝かせ、自主的に学習に取り組むようになりました。
ただし、注意してほしいのは、学習の目的が
「勝ち負け(勝負ごと)」ではない
ことです。
勝ち負けに対して、どうしてもこだわってしまう子もいます。そこは、しっかり伝えた方がいいです。
学習することが「楽しい」「またやりたい」と、知的好奇心をくすぐる感覚を大切にしましょう。
子どもたちの「好きなもの」を取り入れるだけで、授業がぐっと変わる
特別支援教育では、子どもの「好き」を学習に取り入れることが興味関心につながるコツです。
例えば
●好きな歌
●好きなキャラクター➡これ強い!
●好きな動物
●好きな食べ物
●好きな番組
などなど
この「好き」を学習課題に取り入れることで
算数(数学)の授業で、好きなキャラクターを数えることで、数量への理解が深まった。
体育の授業で、好きな音楽を使ってダンスをすることで、模倣するようになった。
と、嬉しい結果がありました。
「好きこそ物の上手なれ」という言葉があるように、「好き」は学習への
最大のモチベーション
と言えると思います。
子どもも教員も楽しく🎵授業
3つの工夫によって、子どもも教員も前向きな変化があります。
【子どもたち】
「今日の授業何するの??(*^▽^*)」と、目がキラキラ
「またやりたい!」と、自信がついて自己肯定感が上がる
【教員】
教材作成の時間が短縮し、授業準備に余裕が出る
授業をすることが楽しくなり、子どもたちとも信頼関係がアップ
子どもにとっても、教員にとっても、「楽しい授業」は大切なのだと、身をもって実感しました。
特別支援教育の授業づくりは、特別なスキルがないと難しいと思われがちですが、
そんなことはありません。
100円ショップで手に入る教材、ゲーム化した活動、「好き」を取り入れる。
この3つを意識するだけで、誰でも子どもたちの「できる」を感じる授業を作ることができます。
今日から、少しずつでもこの3つの工夫を取り入れてみてください。
きっと、教員の余裕、授業の質、子どもたちの表情も変わっていくはずです。

この記事を最後まで読んでいただきありがとうございました。
ご質問等はコメント欄やお問い合わせ欄からどうぞ!
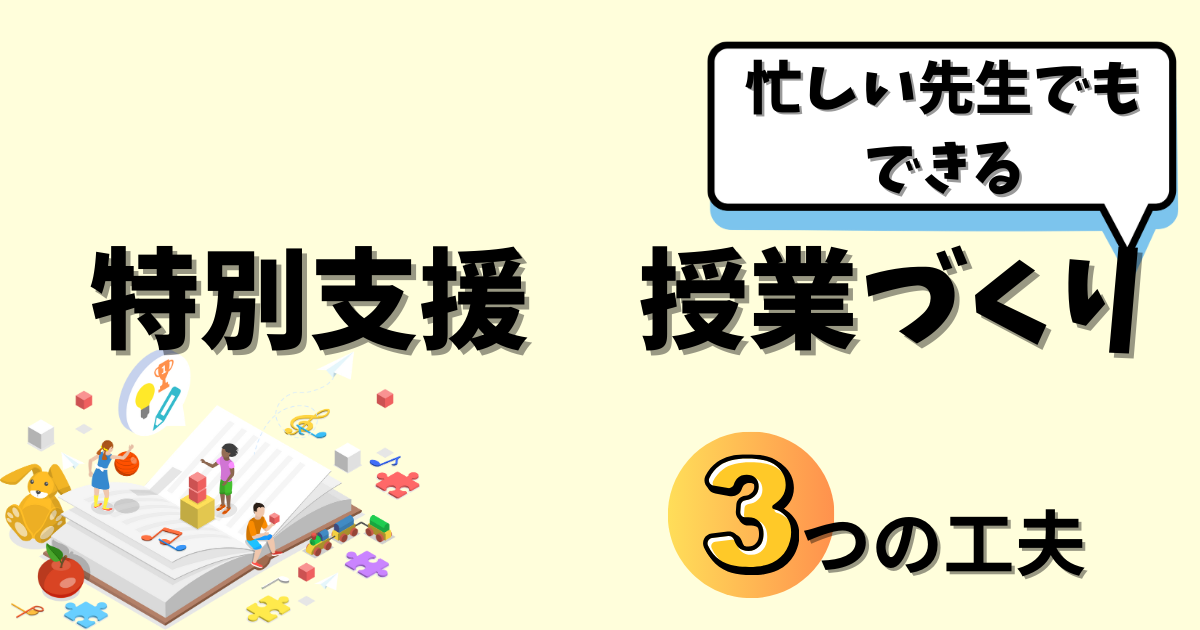

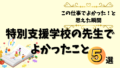
コメント