
「もうこんな時期!個別の支援計画書かなきゃ…」
「個別の支援計画って、ただの事務仕事でしょ?」
「仕事だから一応書いてるけど、実際に何のためにやっているんだろう…」
そんなふうに思ってしまったこと、ありませんか?
実は、この「個別の支援計画」こそが
●子ども
●保護者
●学校
●地域
●医療
これらをつなぐ“羅針盤”なのです。
何で必要なの? ー個別の支援計画を書く理由―
個別の支援計画は、そもそも何のためにあるのでしょうか?
それは、
- 子どもの支援をチームで共有するため
- 保護者との連携を深める
- 支援の方向性を明確にする
ためです。
個別の支援計画は「評価」をしますが、評価をするためだけではなく、
“子どもの成長の道しるべ”
として、大切な役割があります。
私はこんな想いで書いてます
私が常に気をつけていることは、
ただの事務仕事ではなく、子どもや保護者へのラブレターのように書いてみる
ということです。
子どもの実態を書く上で、
●集団活動が苦手
●大きい音が苦手
●見通しが持てないとパニックになる
など、事務的に羅列すると、とても無機質な印象になりますよね。
実態なのだから仕方ない…と思われるかもしれませんが、読み手(子どもや保護者)側からすると
どんな印象をもつでしょうか?
●なんかネガティブ
●できない人間みたい
と、感じませんか?
私は、次のように意識して書いていました。
▶人が多い環境では、不安を感じる様子があるが、パーテーションなどで空間を分けることで、集団活動に参加することができる。
▶大きな音があると耳を塞いでしまうが、イヤーマフをつけることで、落ち着いて活動に向かうことができる。
▶急な予定変更に気持ちが乱れることがあるが、スケジュール表などで視覚的に示すことで、気持ちを切り替えることができる。
実際に保護者との支援計画面談では、
「実態がわかりやすい。」
「子どものことをわかってもらえてると感じ、安心できる。」
との言葉をいただき、信頼も深まりました。
また、ただの書類ではなく、“想いを伝えるツール”なのだと感じました。
意識している3つのポイント
情報は“ストーリー”で整理する
箇条書きで羅列するだけより、「いつ」「どんな」「どのように」など、エピソードの流れや背景がわかると支援者同士、理解しやすくなります。
誰が読んでも、読み手の頭の中に実態が映像化できるような文が望ましいです。
例:①〇年〇月初めてのてんかん発作が自宅にて起こる。
②音楽の授業では、楽器の場面ではイヤーマフをつけるが、鑑賞時にはイヤーマフをつけなくても
参加できる。
子ども‶本人の言葉”で表現する
ネガティブな話題の時には、特に「なぜ それが起こるのか」を、
子ども本人の気持ちになって書きます。
例:×「他害がある」
〇「距離感に不安を感じると、強く関わろうとすることがある」
子ども本人の気持ちになることで、より深く実態がみえてきます。
‶できること”を軸に考える
個別の支援計画では、長期目標・中期目標・短期目標を書きます。
課題(目標)をあげる上で、どうしても「できない」に焦点を当てがちです。
「できない」ことに注目するだけでなく、「できる」ことを「できない」ことの克服にどう
活かしていくかを示すことが大切です。
例:×「はさみを使って切れない」
〇「指の開閉が上手になってきたので、教員と一緒にはさみの操作ができるようになる」
「ここまではできている」から、「次の課題はこれ」と、段階を踏んだ目標であることがわかります。
今日から取り入れて!書き方のコツ
書く前に「対象の子どもの好きなこと、できること」を考える
→ 「こんな未来にしたい!」と、支援の方向性が見えてくる
できることからの課題を明確にする
→ 全体のトーンが前向きに
保護者目線で読んでみる
→ 「難しい言葉を使っていないか」「伝わる言葉」になっているかをチェック
個別の支援計画は「書かなきゃいけない書類」ではなく、
“子どもの今と未来をつなぐ設計図”です。
この設計図の書き方で、子どもたちの未来への道が変わってきます。
私たちは、子どもたちの明るい未来を担っているのです。
今日からまた、子どもたちの未来を再度考えてみませんか?

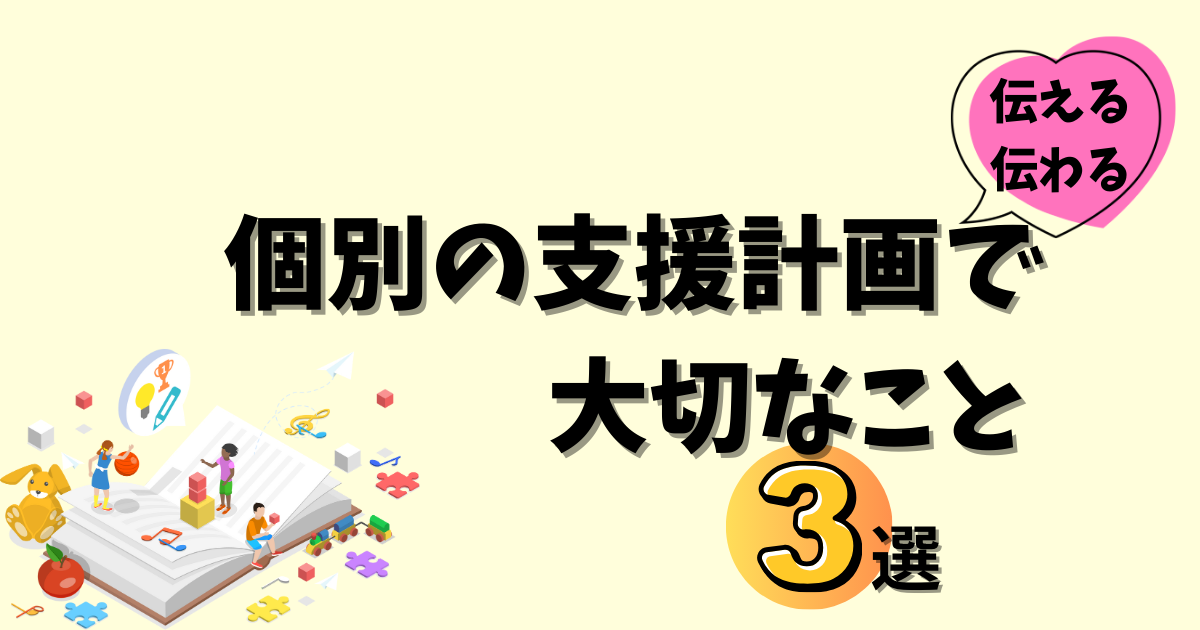


コメント