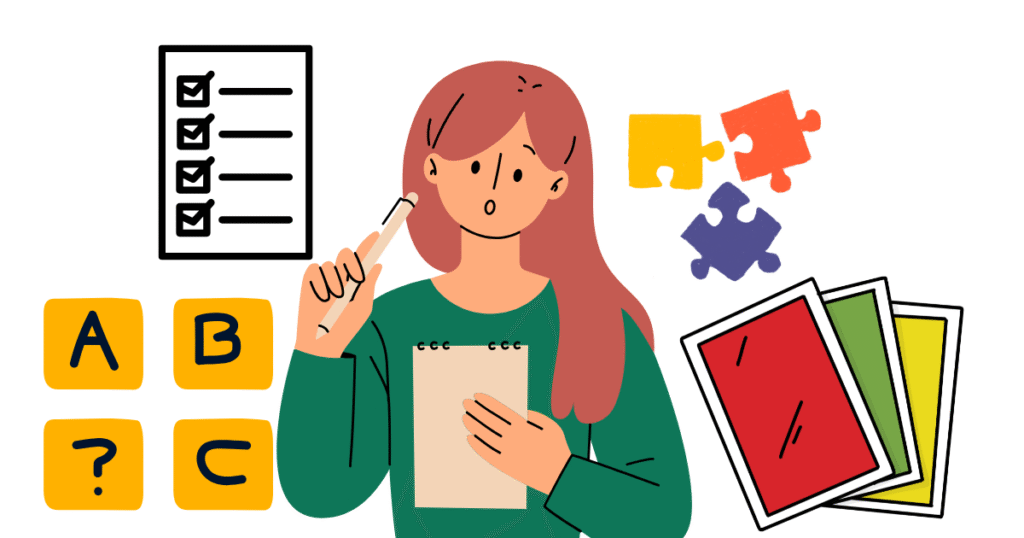
はじめに
「発達・知能検査って、何のためにやるの?」
「結果を見ても正直ピンとこない…」
「結果をどう支援に活かせばいいのか、よくわからない…」
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
私なんて、初めは発達・知能検査の種類さえも知りませんでした。
しかし、特別支援教育に携わる中で、避けて通れないのが「発達・知能検査」。
それを意味あるものにできるかどうかは、理解の深さと活かし方次第です。
今回は、発達・知能検査について特別支援学校の現場でどう活用していくのかをお伝えします。
発達・知能検査を行う意味と目的
教育・支援の出発点としての発達検査
発達検査は、子どもの
- 認知発達(知的能力)
- 言語理解
- 運動機能
- 社会性
などを、多角的に把握するために行われる専門的な評価です。
なぜ必要か?
- 子どもの特性を客観的に捉えるため
- 保護者や関係機関との共通理解を持つため
- 支援の方向性を見つけるため
ただし!検査結果を「ラベル」ではなく、
その子らしい学びやすさを探るツールとして捉えることが大切です。
子どもや保護者と向き合う中で感じること
わたしの経験談
以前面談時に、WISC(ウィスク)検査結果を共有した際、保護者から
「数値を見せられても、何がわかるのか正直わからなくて…」
という声をいただきました。
とても不安そうに結果を見せてくれました。
簡単な結果の所見はありますが、英文字と数値だけではわからないのも当然です。
初任時の私だってそうでした。
ますます保護者は、自分の子どもについて、いったいどういうことなのか不安感が強まります。
それがわかっていたからこそ、私はこの時
「ここが弱いから困っている」
というよりも
「この子は、視覚で理解する力が強いから、絵カードを使うと効果的ですよ」
と伝えるようにしました。
すると保護者の方が、ほっとしたようにこう言いました。
「この検査でこの子の得意なことがわかるんですね!」
検査では、課題となっていること(苦手なこと)と、得意なことがわかります。
どうしても課題に焦点がいきがちですが、得意を知ることも大切な指標です!
発達検査は、子どもを理解する大切なツールです。
それが、現場での実感です。
発達検査の活かし方
支援方法の根拠として活用する
例:ワーキングメモリが弱い子 → 指示は短く/視覚的に伝える
例:言語理解が弱い子 → 短文/実物を用いて伝える
➡数値ではなく支援のヒントを読み取ることが大切です。
教員間・保護者間の共通認識をつくる
検査結果は、支援会議や個別の支援計画作成時の根拠になります。
みんなが「なんとなくそう思ってた」という推測を、
「数値で裏づける」
ことで、共通認識が生まれ、共通の支援指導として使うことができます。
結果をそのまま伝えない工夫をする
結果をそのまま伝えるだけでは、保護者も理解ができないし、それが不信感に繋がることもあります。
➡保護者には、専門用語ではなく日常の行動例で伝える
➡子どもには、「〇〇さんは絵カードで覚えるのが得意なんだね」など、ポジティブにフィードバックする
今日からできる活用のヒント
「発達検査は難しそう」「専門家じゃないし…」と思っていませんか?
でも、明日からできる簡単な工夫もあります!
結果報告時に一緒に伝える言葉例
- 「こういう特性なら、この支援方法が合いそうですね」
- 「困っているというより、やりにくさがあるんですね」
- 「〇〇さんの得意なことを活かしてサポートしていきたいです」
チーム支援での共有ポイント
- 気になる検査指標を教員間で共有
- 実際の行動と照らし合わせて考察
- 「試してみたい支援方法」を具体化して記録に残す
普段の様子とセットで使う
発達検査は、あくまで「参考情報のひとつ」。
日々の子どもの様子とセットで考えることで、より具体的な支援につながります。
おわりに
発達検査が子どもを知る全てではありません。
それは、子どもの「得意」「苦手」「伸びしろ」を探るための地図のようなものです。
理論から学び、
子どもとしっかり向き合い、
実践の中で読み解き、
明日からの支援に活かす。
この4つの視点を意識することで、発達検査は現場で生きるツールになります。
「子どもをわかりたい」
「子どもと保護者に寄り添った支援がしたい」
そんな気持ちがあれば、発達検査は必ずあなたの味方になります!
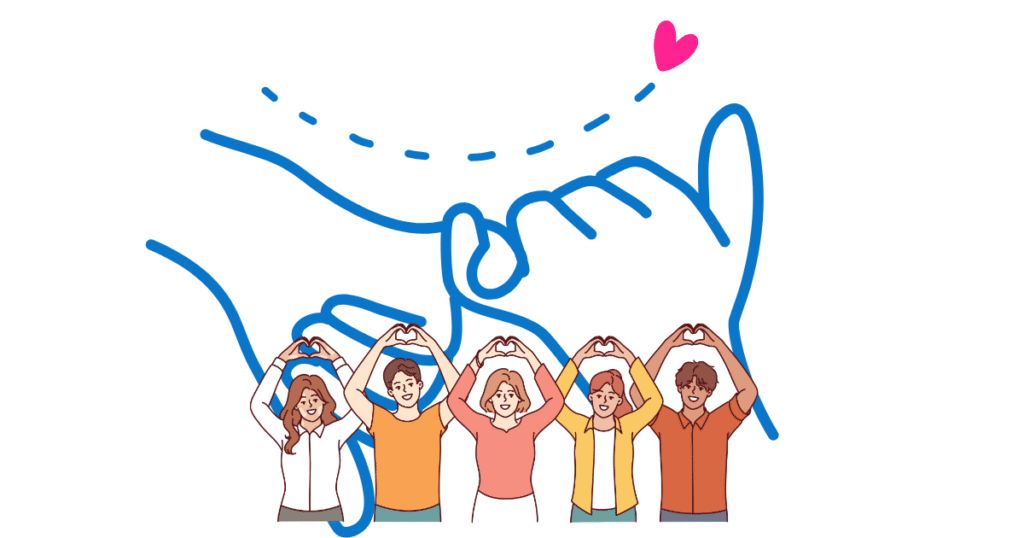
今後も、特別支援学校の授業づくり・支援の工夫について発信していきます。
質問や感想など、コメント大歓迎です♬
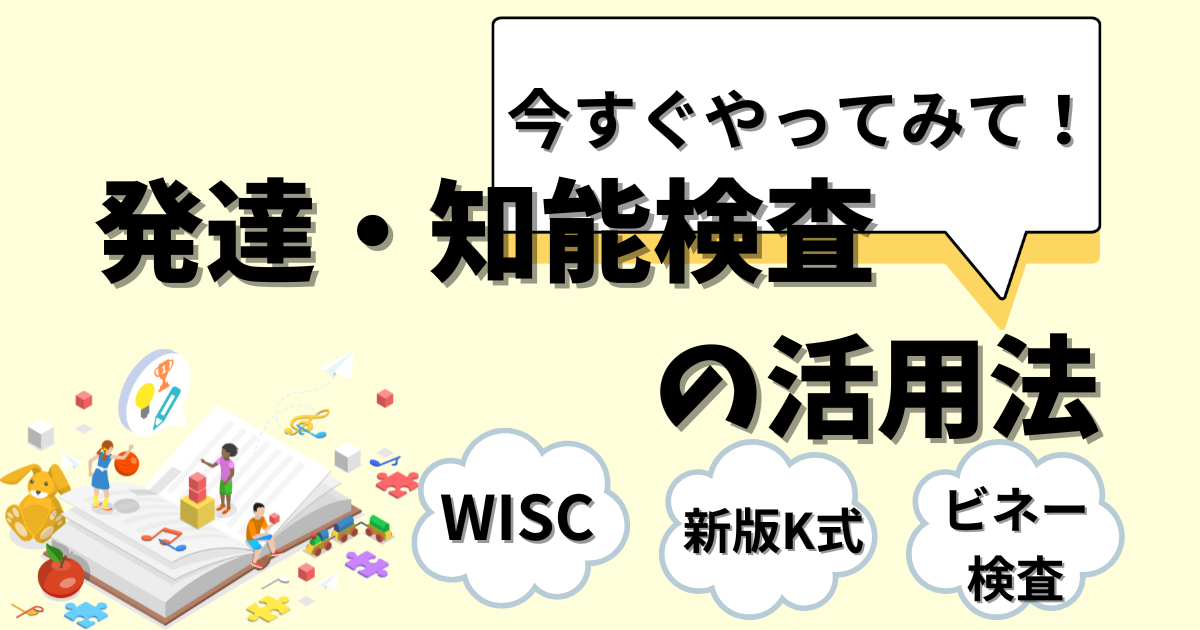
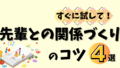
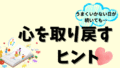
コメント