
はじめに
学校教育の現場では、どうしても
「平均」
「基準」
「普通」
が重視されがちではないですか?
でも!
特別支援教育の現場では、
その子らしさを尊重しながら支援していくことが何よりも大切にされています。
今回は、特別支援教育の魅力である『その子らしさを大切にする教育』についてお話し
したいと思います。
【その子らしさ】を大切にするワケ
特別支援教育は
- 子どもひとりひとりの「得意」と「苦手」を知ること
- 子ども自身が持つ力を、引き出し、伸ばすこと
です。
基準のある成績やテストでは測ることができない
その子のペース
その子の表現
を尊重することで、子どもたちは「ありのままの自分」を認めてもらえる経験を積んでいきます。
このアプローチは、ただの「支援」だけではなく、
その子が社会に出て、生きていく上で大切な基盤にもなるのです。
平均に合わせるのではなく、個性に寄り添うことが子どもたちの心身の成長に繋がるのです。
【その子らしさ】を実感したあの日
以前、ある子との関わりの中でこんなことがありました。
感情の表出が少ないAさん。みんなと同じ活動をすることが苦手でした。
でも…
休み時間や図工の時間などに、好きなアニメキャラクターを描くときだけ、
描いているキャラクターの表情に合わせて、楽しそうに手を動かしていました。
その絵と、楽しそうな様子を学級通信に載せたら、保護者の方からこんなメッセージが!!
「学校でうちの子の笑顔を見たのは初めてです!
こんな風に過ごしているのですね。安心しました。
好きなことを認めてくれる場所を作ってくれて、本当にありがとうございます」
このメッセージを受け取った時、
「私たちが作ってきた環境や支援はAさんにとって間違っていなかったんだ!
Aさんの力をもっと伸ばしたい」
と思いました。
そうなんです。
子どもたちは、言葉ではなく、
表情や行動、好きなことを通して「自分」を表現してくれます。
その小さな表現を見つけ、受け止めること
それが、特別支援教育の魅力だと心から感じています。
「その子らしさ」を引き出す3つの工夫
子どもの得意なこと・好きなことを把握する
- 興味を持っていること(例:電車、絵本、音楽)
- 得意な活動(例:細かい作業、身体を動かすこと)
➔まずは、実態把握です。
興味や得意をベースに、活動や課題を設計すると、子どもたちは自然に意欲を出してくれます。
表現方法に教員の「正解」を押しつけない
- 声で言えないなら、ジェスチャーでもOK
- 絵や写真で伝えることも大事な表現
➔たとえ、教員が求めている表現ではなかったとしても、子どもにとっては正解です。
「話す」「書く」だけにこだわらず、その子に合った伝え方を受け止める姿勢が大切です。
小さな「できた」を一緒に喜ぶ
- 「できた」瞬間を見逃さず、フィードバック
- 小さな成功体験を積み重ねて、自己肯定感を育てる
➔成長のペースは人それぞれ。「今、ここ」の頑張りを認めることが支援につながります。
今日からできるミニアクション
「この子の好きなもの」を知ってみよう
- 好きな遊びは?
- 好きな食べ物は?
- 最近ハマっているものは?
➔そこから会話を広げたり、活動に取り入れたりするだけで、ぐっと距離が縮まります。
できるだけ「正解」を押し付けない問いかけをする
- 「どっちがいい?」(選択肢を提示する)
- 「どんなふうにやってみたい?」(自由な発想を尊重する)
➔自由に自己表現できる空気をつくることが、「その子らしさ」を育てる土台になります。
おわりに
特別支援教育の現場では、
みんなと同じ「できる子」を育てるのではなく
「その子らしく生きる力」を育てる
ことを大切にしています。
できる できない じゃない
話せる 話せない じゃない。
学ぶスピードが速い 遅いでもない。
あなたはあなたでいいよ。
そう伝えられる場所が、特別支援教育なのだと思います。
教員としてこの現場にいることに、私は誇りを感じています✨
みなさんも、ぜひ一緒に、「その子らしさを支える教育」を届けていきませんか

今後も、特別支援学校の授業づくり・支援の工夫について発信していきます。
質問や感想など、コメント大歓迎です♬
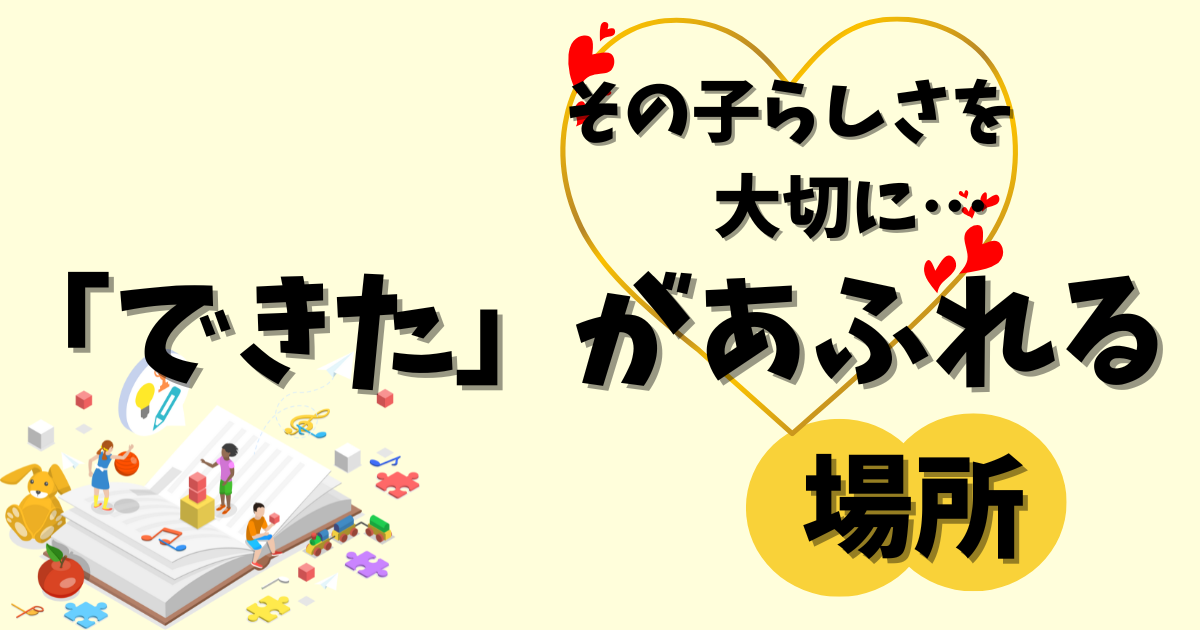
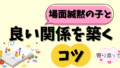
コメント