
私たちが生きるこの社会には、さまざまな「違い」が存在します。
- 見た目
- 話し方
- 考え方
- 育ち方
- できること、できないこと
それは学校の中でも同じことです。
でも!
どこかで「みんな一緒であること」が前提になっている場面、
多い気がしませんか?
社会の中で様々な「多様化」が話題となり、
多様化を受け入れよう!
なんて言葉も耳にしますよね。
受け入れることは、もちろん大事なことです。
しかし、
これからの教育に本当に必要なのは、「違いを受け入れること」ではなく
「違いを楽しめる力」ではないか。
そう思うのです。
「違いを楽しむ力」が求められる理由
教育現場の流行キーワード「多様性」と「共生社会」
近年、教育現場では
●多様性
●インクルーシブ教育
●共生社会
といった言葉が広がっています。
これは単なる流行ではなく、
社会全体が「みんなが同じ」であることを前提にするだけでは
成立しない段階にきているのでしょう。
教育の中で求められる力の変化
これからの教育には以下のような力が求められてきています。
- ひとりひとりの特性を尊重する力
- 違いを認識した上で協力し合う力
- 異なる視点から考える柔軟性と創造性
つまり!
「違いを排除する教育」ではなく、
「違いを受け入れる教育」となり
さらに、
「違いを学びに変える教育」が必要になってきています。
「違い」の中で生まれる学び
実際のエピソードより
ある日のこと。
言葉でうまく話せないCくんと、おしゃべりが大好きなDくん。
言葉が出ないCくんは、絵を描くことが大好き。
コミュニケーションは、ジェスチャーや簡単なサインしか出せません。
それに対してDくんは、
ずっとおしゃべりが止まらないタイプ。
気になることがあると、一方的に話しかけていました。
そんなDくんにCくんは劣等感を抱いている様子もあり、
あまり自分からは近づきません。
もちろん会話にならず、すれ違う場面も多かった二人。
ある日、Cくんが描いた車の絵を見て、
Dくん:「これ、すごくかっこいい!」
Cくん:びっくりした顔をしたが、褒められたことに気づいて笑顔になる。
そこからふたりの関係は一気に変化。
Dくん:「〇〇も描いてよ」
Cくん:戸惑いながらも、描いてあげる
Dくん:「すごーい!」
Cくん:言葉は出ないが、嬉しそうな表情😊
会話ではなくても、表現や感性で通じ合うことができると、お互いが気づいた瞬間でした。
「違い」は気まずさではなく、新しい興味や、つながりのタネ
違うからこそ、「へぇ〜!」「そんな考え方あるんだ!」と学びが生まれます。
言葉があってもなくても、通じ合えることはあります。
表現の方法が違っていても、「こんな表現があるんだ」と興味をもって楽しむこと。
それが本当の意味での「多様性の学び」ではと、考えます。
「違いを楽しむ力」を育む実践例
実践①:「みんな違って、みんないい」ワーク
▶子どもたちに「好きな○○」を出し合ってもらう
例えば…「好きな色」「好きな音楽」など
自由に発表し、自分と違う意見でも「それもいいね!」と
お互いにリアクションする時間を大切にします。
実践②:ゴールを1つにしない授業設計
制作活動や体育などで「できる・できない」がはっきりと分かれる場面では、
「それぞれのゴール」を用意すると、
子どもたちは安心して取り組めます。
▶ハサミが苦手なら手でちぎってOK
▶走るのが苦手なら応援担当もOK 歩いてゴールもOK
実践③:教員が「違いを楽しむ姿勢」を見せる
▶「それいいね!」
▶「そんな方法もあるんだ」
と、教員自身が違いを肯定する姿を見せることで、クラスの空気も変わっていきます。
「同じじゃなくていい」「違ってもいいんだ」「違うこともおもしろい」と、
子どもたち同士も「違い」に抵抗感がなくなります。
いますぐ! 教室でできる“違いを楽しむ”ミニアクション
今日からできる小さなアクション
- 「正解はひとつじゃない」と伝えてみる
- 発表の方法を選べるようにする(話す・描く・ジェスチャーなど)
- 違う意見や行動を見つけたときに「それ面白いね」と言ってみる
- 教員自身も自分の得意・苦手を共有する(例:「先生は音楽は苦手だけど、図工は得意!」)
小さな「違いを肯定する言葉」が空気を変える
授業中や生活の中で、
「それもいいね」
「やってみようか」
と、声をかけるだけでも、「違っていてもいいんだ」という安心感が育ちます。
これからの教育に本当に必要なのは、
「みんなと同じにする力」ではなく、
「違いを楽しむ力」です。
それは子どもたちにとっても、教員にとっても、生きる力になるものです。
まずは私たち教員が、違いを
「不安」ではなく
「ワクワク」で見つめていきたいですね。
明日の教室から、少しずつ「違いを楽しむ一歩」を始めてみませんか?

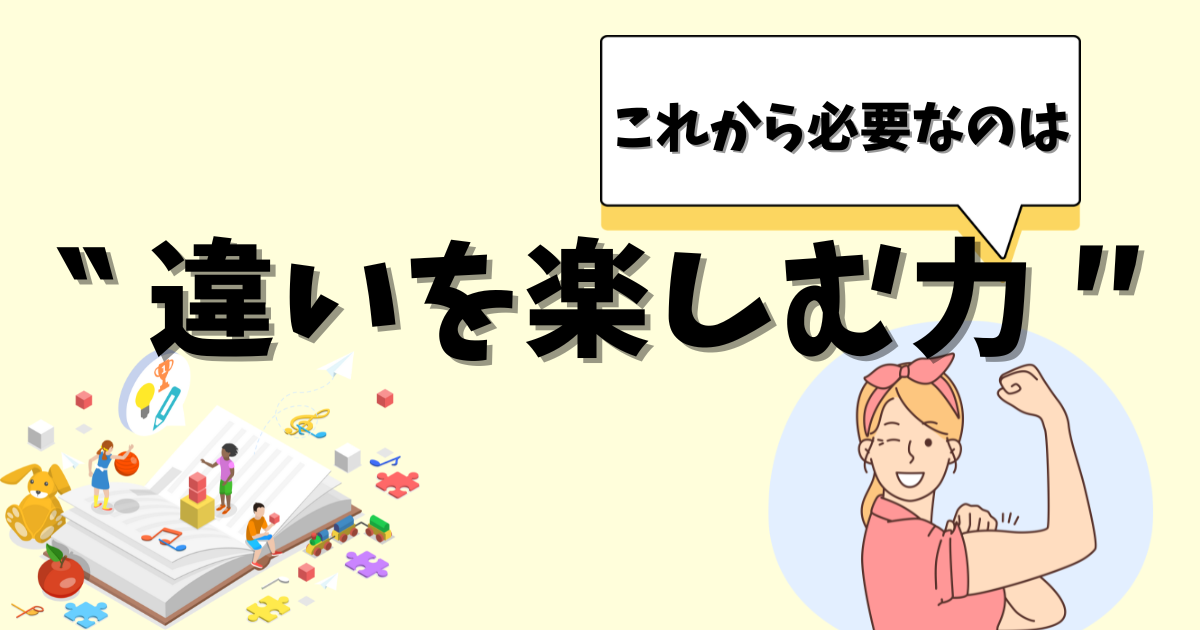
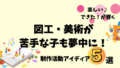
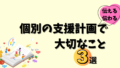
コメント